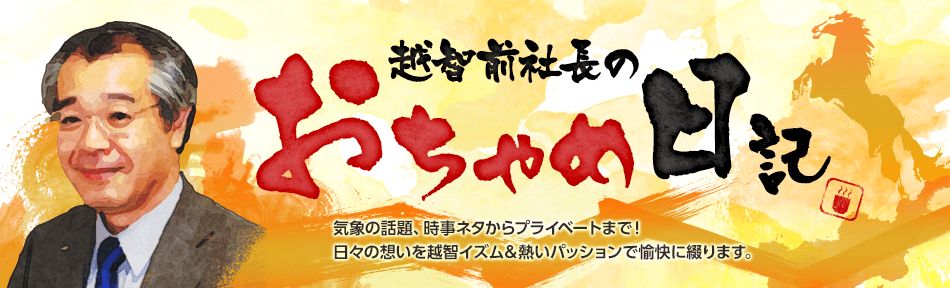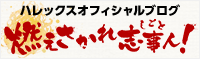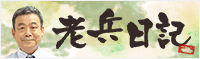2017/09/08
エッ! 邪馬台国は四国にあった? (その6)
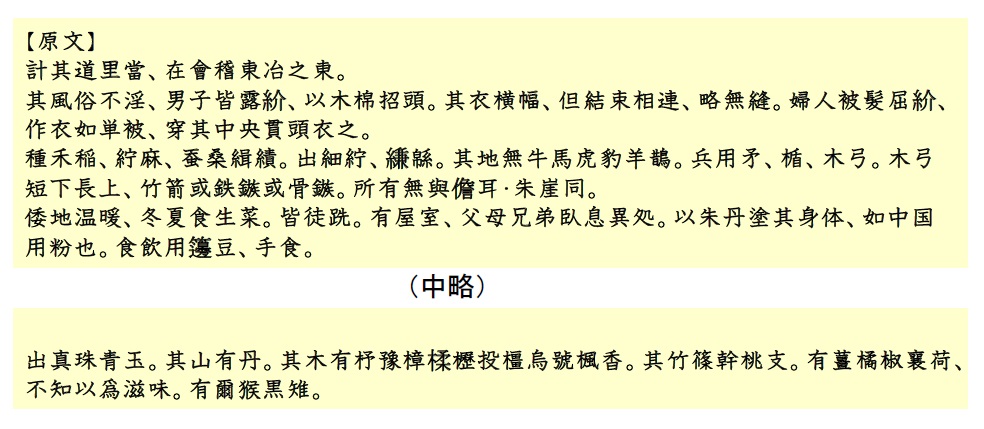
【現代語訳6】
その行程を計測すると、倭国は会稽の東にあることになる。
その風俗は淫らではない。男子は皆かぶりものをせず、木綿を頭に巻いている。衣服は横幅衣でただ結んで束ねてつなげ、ほとんど縫っていない。女性は束ねた髪を結っていて、衣服は中央に穴をあけ、そこから頭を出して着ている。
稲や苧麻を植え、桑で蚕を飼い、紡いで細い麻糸、綿、絹織物を作っている。
その土地には、牛、馬、虎、豹、羊、鵲(セキ)はいない。
武器は矛、盾、木の弓を用い、弓の下部を短くして上部を長めにしている。竹の矢に鉄の矢じりや骨の矢じりを用いる。産物の有無はタンジ(地名?)や朱崖(地名?)と同じである。
倭の地は温暖で、冬でも夏でも生野菜を食べる。みな裸足である。家屋には居室があり、父母兄弟は寝るところは別々である。中国で粉を用いているように、朱丹を体に塗っている。飲食(の食器)には高杯を用いて、手掴みで食べる。
上記は魏志倭人伝の第2章「倭國の風俗」にあたる部分の抜粋です。この文の冒頭に登場する会稽とは中国の秦代から唐代にかけて存在した郡の名称で、揚州東部の長江下流域、現在の中華人民共和国浙江省紹興市付近がその中心とされています。「倭国は会稽の東にあることになる」と書かれていますが、倭國の中心(邪馬台国)が四国にあったとすると、まさにその通りの位置関係です。
上記の文中に「その土地には、牛、馬、虎、豹、羊、鵲(セキ)はいない」という一文があります。そこに出てくる鵲(セキ)とは“カササギ”のことです。カササギは、スズメ目カラス科に属する翼を広げると幅が60cmほどになる比較的大型の留鳥で、別名をカチガラス、もしくはコウライガラス(高麗烏)といいます。標高100m 以上の山地には生息せず、人里を棲家(すみか)とし、人里の大きな樹の樹上に球状の巣を作り繁殖します。コウライガラス(高麗烏)の名のとおり朝鮮半島では極々身近な鳥で、吉兆の鳥とされ、韓国では“国鳥”とされています。なので、朝鮮半島にある帯方郡からやって来た役人は、牛、馬、虎、豹、羊という獣に混じってわざわざ鵲(セキ)、すなわち“カササギ”という鳥のことを取り上げて、「鵲はいない」と報告したのだと思います。
Wikipediaによると、このカササギ、日本では北海道、新潟県、長野県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県で繁殖が記録されていて、秋田県、山形県、神奈川県、福井県、兵庫県、鳥取県、島根県、宮崎県、鹿児島県の各県、島嶼部では佐渡島と対馬で生息が確認されているとされています。主に九州北部をはじめとする日本海側にしか生息していない鳥で、日本では生息地ごと天然記念物に指定されています。ちなみに、“カササギ”は佐賀県の“県鳥”で、佐賀県にあるサッカーJ1のチーム「サガン鳥栖」のエンブレムやマスコットにも使用されています。生息分布が現在とは微妙に異なるかもしれませんが、昔いた鳥が絶滅していなくなることはあっても、昔いなかった鳥がその後いるようになって、おまけに生息地を定めた国の天然記念物、さらには県という自治体を代表する“県鳥”に指定されるというのはよっぽどのことです。このことは、大変に申し訳ないことですが、北部九州に邪馬台国はなかった…ってことを意味するのではないかと私は思うのですが…。で、このカササギ、標高100m 以上の山地が多い四国ではこれまで生息が確認されておりません。もちろん、四国には野生の牛や馬、虎、豹、羊も生息していません。
佐賀県公式HP
また、倭の土地は一年中裸足で過ごせるほど温暖であること。稲や貯麻(カラムシ)を植え、桑で蚕を飼って紡績をおこない、麻糸・絹・綿を産出すること。冬でも夏でも生野菜を食べること…等が書かれています。この文章を読む限り、邪馬台国が四国にあったことを否定するものは何一つ見つからないのですが、反対に、この魏志倭人伝の第2章「倭國の風俗」にあたる部分の続きには、邪馬台国が四国にあったことを裏付ける極めて決定的な一文があるのを見つけました。それがこれです。
【現代語訳6´】……原文は【原文6】後半参照
真珠、青玉を産出する。山には丹を産出する。樹木には、トチノキ、クスノキ、?、クヌギ、?、カシ、?、カエデ等があり、竹類には、ササ、ヤタケ、カヅラダケ等がある。生姜、橘、山椒、茗荷もあるが、滋味ある食物として利用することを知らない。猿や黒雉もいる。
トチノキ、クスノキ、クヌギ、カシ、カエデ…といった温暖な地に自生する落葉広葉樹や常緑広葉樹の名称が並んでいることから、邪馬台国は本当に温暖なところにあったということなのでしょうね。生姜や橘、山椒、茗荷も自生しているということですから、なおのことです。
で、ここで注目すべきは、この段落の先頭の「“真珠”、“青玉”を産出する。山には“丹”を産出する」という一文です。
“真珠”はここで私が申し上げるまでもありません。愛媛県の宇和海は日本最大の真珠の生産地です。現在、宇和海の真珠は養殖がほとんどですが、量・質ともに日本一の真珠が採れるということは、温暖な海水とリアス式海岸の小さな入り江が連なる穏やかな宇和海が、もともとアコヤガイをはじめとする貝類が真珠を生成するのに適した極めて恵まれた自然環境にあるということです。日本は古くから真珠の産地として有名だったのですが、現在真珠の養殖で知られている宇和海や英虞湾(三重県)では古くから天然の真珠が豊富に採れていたところだったのではないか…と容易に推定されます。その宇和海(投馬国)で採れた真珠は、おそらく現在の国道439号線(高知県の四万十市から四国山地の山中を東西に横断するように徳島県徳島市まで延びる道路)を使って邪馬台国の卑弥呼のもとに届けられたのでしょう。(写真は愛媛新聞社様からご提供いただいたものです:2013年8月22日付「宇和 真珠」 G20180501-04214)

注目すべきは次の“青玉”です。皆さんは「伊予の青石」、「石鎚の青石」という石があるのをご存知でしょうか。青々とした色と変化に富んだ模様が美しい全国的にも珍しい石で、古都京都をはじめ日本全国の数々の名庭園に景石として使用されています。「伊予の青石」、「石鎚の青石」の名前の通り、主に愛媛県の中部で採れる岩石で、西日本の中央構造線に沿った三波川変成帯に分布し、三波川結晶変岩と言われています。特に、西条市、西日本最高峰の石鎚山から流れ出る加茂川流域が一番の産地で、賀茂川流域の河川で採れる川砂利や川石の中から容易に見つけることができます。西条市を流れる賀茂川や中山川の上流あたりに行くと、なぁ~んとなく岩が暗い緑色をしていることに気がつかれると思います。それがこの「伊予の青石」、「石鎚の青石」です。私は母の実家が西条市(旧周桑郡丹原町)にあった関係で、子供の頃、よく中山川の河原で遊んだことがあるのですが、そこで宝石のように鮮やかな青緑色をした「伊予の青石」、「石鎚の青石」を拾って、大事に家に持ち帰った記憶があります。(写真は愛媛新聞社様からご提供いただいたものです:2007年8月11日付「加茂川」 G20180501-04215)

この青石、正式名称を緑泥片岩(クロライト)と言います。アルミニウムや鉄、マグネシウムを含むケイ酸塩鉱物である“緑泥石”を主成分とする結晶片岩で、何億年も前に海底に堆積した土砂が大陸プレートの沈み込みによって地下20km~30kmの深さに潜り込み、温度約200℃~300℃、約600~700気圧と言う比較的低温高圧の変成作用を受けてゆっくりと形成された岩石です。その地中深くにおいて形成された岩石が日本列島の背骨とも言える中央構造線の隆起によって、さらに何億年という長い年月をかけて再び地表に現れたものです。北西方向に進んできた密度の高い海洋プレートであるフィリピン海プレートが、密度の低い大陸プレートであるユーラシアプレートと衝突してその下に沈み込む南海トラフが四国のすぐ南の太平洋の水深約4,000mの深い海底にあり、さらには、そのすぐ近くに今も何億年もかけてゆっくりと隆起活動を続ける中央構造線が東西に走る四国、それも愛媛県の西条市付近でしか採れない美しい石なのです。
(その5)に示す大杉博氏の考察によると、現在の西条市あたりには都市国家連合として邪馬台国を支える国々であった姐奴国、對蘇国、蘇奴国があり、そのあたりでたくさん採れた青玉はおそらく陸路(香川県の坂出市から剣山の8合目付近に延び、そこで国道439号線と合流する現在の国道438号線)を使って邪馬台国の卑弥呼のもとに届けられたのではないか…と考えられます。
西条市公式HP
また、新居浜市から西条市にかけての中央構造線に沿った三波川変成帯には、「えひめ翡翠(ヒスイ)」と呼ばれる大変美しい緑色をした岩石を産出する場所があります。翡翠(ヒスイ)と称していますが、正式な鉱物名としてはスメクタイト(ニッケル珪質岩)と呼ばれ、残念ながら宝石の翡翠(硬玉)とは全く異なる種類の鉱物なのですが、翡翠と非常によく似た美しい緑色を呈していることから「えひめ翡翠」と呼ばれ、翡翠に比べて硬度が低く(柔らかく)、勾玉(まがたま)等への加工が容易なことから、古代には翡翠の代用品としてむしろ重宝がられたようです。(余談:鉱物学的には「翡翠」と呼ばれる石は化学組成の違いから「硬玉(ジェダイト:ヒスイ輝石)」と「軟玉(ネフライト)」に分かれます。実は中国では軟玉しか採れず、古代中国では軟玉の翡翠が価値ある宝石とされ、“玉”と呼ばれてきました。「えひめ翡翠」はその「軟玉」に類するものと捉えればよろしいかと思います。)
翡翠の名称にふさわしく鮮やかな緑色を発色する素になっているのが金属のニッケル(Ni)。実は宝石の翡翠も化学的に純粋なヒスイ輝石の結晶は無色で、翡翠はこのヒスイ輝石の細かな結晶の集まりのため白色となります。翡翠が鮮やかな緑色等の様々な色を持つのは石に含まれる不純物である鉱物が発色する色のためです。日本では翡翠は鮮やかな深緑色の宝石という印象が強いのですが、鮮やかな緑色のものはクロム(Cr)やニッケル(Ni)、落ち着いた緑色は二価鉄(Fe)が発色の原因となっています。「えひめ翡翠」は宝石の翡翠とは鉱物としては別の種類のものですが、含まれる含有物は極めて似ています。前述の「伊予の青石」、「石鎚の青石」もおそらくニッケルやクロムを大量に含んだ結晶片岩だったということなのでしょう。
ニッケル(Ni)は耐食性、熱伝導性、電気伝導性に優れ、現在ではステンレス鋼の材料であるため需要は極めて多い金属です。光沢があり耐食性が高いため装飾用のメッキ(鍍金)に用いられることも多く、また武器製造に使用する特殊鋼や薬莢の材料である白銅の原料として極めて重要であるため、国家が備蓄し、平時は硬貨として流通させ、有事に際しては他の素材の硬貨や紙幣で代替して回収したりするほどの金属です。日本でも第二次世界大戦直前の昭和8年(1933年)から昭和12年(1937年)にかけて、5銭と10銭のニッケル硬貨が発行されているのですが、その目的は迫り来る戦争に備えるためでした。翡翠と見紛うほどの美しく輝くような緑色をした石が採掘されるということは、それだけ純度の高いニッケル鉱が採れるということで、西条市の加茂川流域には、かつてニッケルを採掘するための黒瀬鉱山という鉱山がありました。黒瀬鉱山は、当初、石筆や白墨などの原料となる滑石(かっせき:水酸化マグネシウムとケイ酸塩からなる鉱物)の採取を目的に大正時代に開坑した鉱山なのですが、採掘の途中で大規模なニッケル鉱床の露頭を発見してニッケルを対象にした鉱山に移行。第二次世界大戦終結までニッケルの採掘を継続したのですが、戦後は再び滑石の採取に戻りました。しかし、安価で良質な滑石やニッケルが海外から大量に輸入されるようになり、昭和26年(1951年)に操業を休止。閉山されたまま、現在は黒瀬ダムの湖底に眠っているようです。
余談になりますが、四国を東西に貫き、標高1,982メートルの西日本最高峰の石鎚山を含む四国山地という天険を形成する大断層帯である中央構造線。中央構造線は地中深くで生成された鉱物が激しい断層活動で地上付近にまで押し出されてきたようなところです。特に四国中央市(旧宇摩郡土居町)と新居浜市(旧宇摩郡別子山村)の境界に位置する標高1,706mの東赤石山周辺にはマントル物質と見られる橄欖(カンラン)岩、さらには橄欖岩が水を含んで変質した蛇紋(ジャモン)岩が広く分布しています。また、東赤石山から西には三波川変成帯のうち三縄層と呼ばれる地層にはキースラガーと呼ばれる含銅硫化鉄鉱の鉱床が地表付近に集中して発見されていて、別子銅山もその一つです。三波川変成帯は地下資源の宝庫とも呼べるところで、別子銅山(黄銅鉱・鉄)以外にも、佐々連(さざれ)鉱山(金・銀・銅・鉛・亜鉛・硫化鉄)、新宮鉱山(銅・鉄鉱石)、基安(もとやす)鉱山(銅)、愛媛鉱山(銅・亜鉛・磁鉄鉱)、市之川鉱山(アンチモン)、報国鉱山・鞍瀬鉱山(マンガン)、赤石鉱山(クロム)…など多くの鉱山があり、採掘される金属も銅や鉄だけでなく、実に様々なものがありました。
また、三波川変成帯とは外れますが、中央構造線沿いには伊予郡砥部町に古宮鉱山(銅・水銀・マンガン・アンチモン)、広田鉱山(銅・硫黄)、横道鉱山(輝安鉱)、銚子滝鉱山(金・銀・銅・アンチモン)、万年鉱山(アンチモン)といった小規模の鉱山がありましたし、伊予市中山町には中山鉱山、寺野鉱山、二川登鉱山、佐礼谷鉱山といった銅や硫化鉄が産出される小規模の鉱山が幾つかありました。喜多郡内子町には愛媛県第2位の銅の採掘量を誇った大久喜鉱山がありましたし、佐田岬半島周辺にも幾つかの小規模な銅鉱山がありました。中央構造線の南側にあたる南予地域にも、生山鉱山、蔵貫(くらぬき)鉱山、大平鉱山、明間(あかんま)鉱山といったマンガンが採掘できる鉱山がありました。ちょっと調べただけでも、ここに書ききれなかった小規模の鉱山が他にもいっぱいありますが、すべて掘り尽くしたのか、あるいは海外からの安価な輸入品に押されたのか、上記の鉱山はすべて既に閉山されています。愛媛県に限らず、徳島県にも多くの鉱山の跡が残っていて、四国の中央構造線に沿った一帯は、今では考えられませんが、かつては鉱物資源の宝庫のようなところでした。このことも四国の歴史を探求するうえで、極めて重要なキーワードになります。写真は良質なアンチモンが採掘されることで世界的に有名だった西条市の市之川鉱山跡に残る千荷坑です。現在はコンクリート壁で塞がれています。四国、特に愛媛県の中央構造線沿いにはこうしたかつての鉱山跡が多数残されています。(写真は愛媛新聞社様からご提供いただいたものです:1999年7月24日付「市之川鉱山跡」 G20180501-04216)

いずれにしても、「伊予の青石」、「石鎚の青石」、「えひめ翡翠」…と、愛媛県は古くから美しく輝く宝石のような青緑色をした石を産出するところとして有名で、魏志倭人伝に出てくる“青玉”とは、おそらくそれらの石を勾玉(まがたま)等に加工したもののことを指すと思われます。
そして、これも鉱物資源に関することですが、魏志倭人伝の中に書かれていることでさらに決定的なことが“丹”を産出するという一文です。“丹”とは辰砂(硫化水銀)のことです。希少金属である水銀(Hg)はこの丹(辰砂)を精錬することにより採れます。辰砂、すなわち硫化水銀(HgS)は地球の内部にあるマグマや水脈の中で約650℃~1000℃、2000気圧~4000気圧といった高温、高圧力の中で生成され、地殻変動(中央構造線の隆起)によって何億年もの年月をかけて地表に押し上げられることにより徐々に温度と圧力が低下し、長い時間をかけて少しずつ結晶体に成長してできたものです。中央構造線が東西に横切るように通る四国山地の一帯は、その昔、辰砂(硫化水銀)の一大産地でした。ちなみに、徳島県阿南市水井町にある若杉山遺跡からは辰砂から硫化水銀を取り出す際に用いたと思われる石臼や辰砂そのものの原石が発見されており、3世紀半ば過ぎから7世紀末頃までの古墳時代における水銀採取遺跡として知られています。3世紀半ば過ぎと言えば、まさに魏志倭人伝が書かれた時代、邪馬台国と卑弥呼の時代です。
魏志倭人伝の第2章「倭國の風俗」にあたる部分には「中国で粉を用いているように、朱丹を体に塗っている」という表現もありました。昔は水銀(塩化水銀)を用いた白色顔料(いわゆる白粉(おしろい)です)が化粧品として広く使われていましたが、ここでは朱丹、すなわち赤色をした丹を体に塗っているということです。辰砂(硫化水銀)はまさに不透明な赤褐色の塊状、あるいは透明感のある深紅色の菱面体結晶として産出されます。おそらくそれを粉末に粉砕して体に塗っていたということでしょう。それも一般庶民が普通に体に塗っていたということは、それだけ大量に丹が採れていたことを意味しています。
また、魏志倭人伝の文章を読むと「出真珠青玉、其山有丹」と、真珠と青玉は“出る”という表現なのに対して、丹は“山に有る”という表現をしています。ここに微妙な差を感じます。すなわち、真珠と青玉はたいして苦労をせずとも海や河原でいっぱい採れる、言ってみれば“拾える”という意味で、丹は山にあるのだけれど、手間をかけて掘り出し、精錬しないといけないという意味の微妙な違いなのではないでしょうか。もしそうだとすると、魏志倭人伝を含む三国志を西晋の初代皇帝・司馬炎(武帝)に命じられて編纂した陳寿は、メチャメチャ博識で文才がある相当実務能力の高い人物だということができます。おそらく現代に生きていてもトップクラスのビジネスマンになっていたのではないかと想像できます。
ちなみに、魏志倭人伝の一番最後の文章は次の通りです。
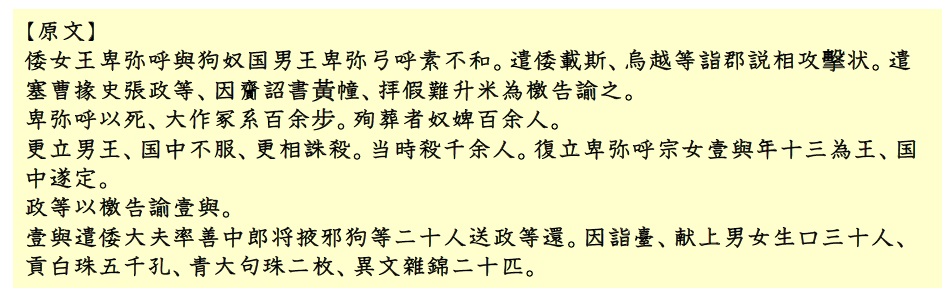
【現代語訳7】
倭の女王卑弥呼は、もとから狗奴国の男王卑弥弓呼と不和であった。倭の載斯烏越らを帯方郡に送って、狗奴国と攻撃しあっている様子を報告した。郡太守は塞曹掾史張政等を遣わし、詔書と黄幢を難升米に授け、激文をもって卑弥呼に告諭した。
卑弥呼が死んだ時、倭人は直径百余歩の塚を盛大に作った。奴稗百余人が殉葬された。
あらためて、男王を立てたが、国中が服さず、お互いに殺し合った。この時千余人が殺された。再び卑弥呼の宗女の壱与という十三歳を立てて王とし、国中はやっと治まった。
張政らは激文を発して、壱与に告諭した。壱与は、倭の大夫率善中郎将掖邪狗ら二十人を派遣し、張政等が帰国するのを送らせた。
このおり掖邪狗らは洛陽に行き、男女の奴隷三十人を献上し、白珠(真珠)を五千個、青く大きい勾玉(まがたま)二枚、異文雜錦二十匹を献上した。
その一番最後の部分に「白珠(真珠)を五千個、青く大きい勾玉(まがたま)二枚、異文雜錦二十匹を献上した」と書かれています。もちろんその勾玉は青玉(伊予の青石、あるいはえひめ翡翠)を加工したものでしょう。“異文雜錦二十匹”とは、様々な色糸を用いて織り出された異なる柄の絹織物20反という意味ではないかと想像します。魏志倭人伝には「稲や苧麻を植え、桑で蚕を飼い、紡いで細い麻糸、綿、絹織物を作っている」という一文もありますから、絹織物も当時の邪馬台国の特産品だったのでしょう。献上品は一目見ただけで自国の凄さを自慢できる、あるいは自国の魅力を誇示できるような特産品を贈るのがふつうだったでしょうから、大量の美しい真珠と、「伊予の青石」や「えひめ翡翠(軟玉)」といった青玉を加工した美しい勾玉、そして色鮮やかな絹織物は邪馬台国(及びその周辺の連合都市国家)を代表するような特産品だったってことがこの一文から読み取れると思います。
もうこれは論理的に否定しようもない決定的な証拠になりますね。“状況証拠”が恐ろしいくらいに揃いすぎています。この「真珠と青玉と丹を産出する」という一文の存在を持ってすれば、もうこれだけで邪馬台国は四国にあったと言わざるを得ません! むしろ、邪馬台国があった場所を特定するためには、まず「海に囲まれた島の中にある周囲が400~500kmのところで、海を挟んで東に約80km行ったところに比較的大きな陸地があり、温暖で、稲や貯麻(カラムシ)を植え、桑で蚕を飼って紡績を行い、麻糸・絹・綿を産出することができるところ。また、冬でも夏でも生野菜を食べることができ、裸足で過ごすことができるところ」の中から「カササギが生息していなくて、真珠と青玉と丹を産出する場所」ということで大まかな候補地を選び、その場所の中から第25回で述べた邪馬台国までの旅程を当てはめて、さらに詳細な場所の特定を行う…といったアプローチのほうが論理的で、より近道なのではないのか…と思えるほどです。
実は私はこの順番によるアプローチで、邪馬台国は四国にあったという大胆すぎるくらいに大胆な仮説を導き出しました。最初は、徳島県に邪馬台国は四国、それも徳島にあったという説があることを知り、それに興味を持ち、邪馬台国が四国にあったのだとしたら面白いだろうな…、四国も元気になるだろうし…くらいのほんの軽~い気持ちで始めた調査でした。始めた当初は正直半信半疑、と言うか、実はほとんど信じていませんでした。
邪馬台国や卑弥呼のことが書かれている文献と言えば魏志倭人伝ですから、面白そうだし、それなら取り敢えず魏志倭人伝を原本で全て読んでみようと思い、漢字だらけの原文にザッと目を通してみました。その時に目に止まったのが“真珠”と“青玉”、“丹”という3つのキーワードでした。それを目にした時、「エッ!?」っと強い衝撃を受け、最初に詳しく読んでみたのが、そのキーワードが載った第2章にあたる中盤の「倭國の風俗」が書かれた部分でした。私は「社会の最底辺のインフラは地形と気象」という基本的な考え方を持っていますから、まずはゴールとなる邪馬台国の風土を知るところから始めたわけです。そこを読んでいくうち、これまで述べてきたように「魏志倭人伝に書かれた邪馬台国の地理的条件、気象的条件にこんなにピッタリ合致する場所は、日本中探しても四国しかない!」と確信に近いものを感じて、それでは次にそれを検証してみようと第1章にあたる部分に書かれている邪馬台国への道程の読み解きに取りかかったわけです。ゴールにある程度確信が持てていないと、いくら邪馬台国までの道程について長い時間をかけて真剣に考えてみたとしても、最後は無駄な徒労に終わるというものですから。
また、これまで邪馬台国のあった場所の特定に取り組んで来られたそれこそ何百人、何千人もの歴史学を専門となさっている歴史学者の先生方、さらにはその10倍、いや100倍はいらっしゃるであろう歴史マニアと呼ばれる人達とは根本的に異なるアプローチでこの日本の古代史最大の謎の解明に取り組んでみようと思いました。それで、言ってみれば、魏志倭人伝に書かれていることを後ろ(ゴール)から逆に辿ってみる…という“逆からのアプローチ”をとってみたわけです。これって、実はコンピュータシステムのトラブルシューティングにおいては常套手段のように用いられる極々基本的な手法です。まぁ~、今年(2016年)は閏年で、四国遍路も「逆打ち」のほうが功徳が大きいとされていますからね(笑)。
—
(注: 本稿「その1」の冒頭に記載のとおり、この内容は2016年10月と11月に愛媛新聞社が運営する会員制Webサイト『愛媛新聞Online』のコラム『晴れ時々ちょっと横道』に連載されたものです。)
—
邪馬台国への道程の読み解きに関しても、実は逆からのアプローチでした。最初に取り組んだのは、一番最後の投馬国から邪馬台国に到る「陸路1ヶ月」の謎の解明でした。なので、四国山地の深い山中を東西に横切る国道439号線の存在を知った時には、正直鳥肌が立ちました。最大の難問と思えた一番最後の投馬国から邪馬台国に到る「陸路1ヶ月」の謎が一気に解けた感じがして、邪馬台国は四国、それも徳島県の剣山の麓にあったという仮説に対する確信は、より強固なものになりました。朝鮮半島の帶方郡や狗邪韓国から投馬国までの道程も、実は魏志倭人伝に書かれている道程を逆に読み解いていきました。逆に道程を読み解いていくと、途中、末盧国から不彌国までの区間で一時的に陸路を使うという不思議な道程の意味、と言うか必要性(途中に関門海峡という海の難所が立ちはだかること)は、すぐに理解することができました。地形や気象が今と変わらない以上、昔の人も考えることは現代人とさほど変わりませんから。それで第25回でご紹介した大胆すぎるくらいに大胆な仮説が生まれたわけです。あとは、この仮説を裏付ける実証をネットで自治体などの公的な機関が出している信頼できるサイトの中から見つけて、その仮説に徐々に肉づけをしていくだけでした。
このように『魏志倭人伝』を素直に読んで、そこに書かれているとおり論理的に考えていくと、どう考えてみても邪馬台国は四国、それも徳島県の剣山の麓にあったとしか考えられないのです。いかがですか? 私のこの大胆すぎるくらいに大胆な仮説。後は決定的な“物的証拠”を見つけ出すだけです。これは地元にお住いの方々にお任せしたいと思います。邪馬台国があったのは間違いなく徳島県の剣山の麓。ですが、その解明のための重要な鍵は、実は愛媛県が握っているというわけです。特に邪馬台国への途中経路にあたると推定している南予地方の調査が重要な鍵を握ると私は考えています。これまでの邪馬台国論争ではノーマークで、誰も手を付けてこなかっただけです。その気になって探せば、いろいろと面白い物証が出てくるのではないか…と私は大いに期待しています。(反対に北部九州と畿内ではいくら探しても邪馬台国がそこにあったという決定的な証拠が見つからない筈です。もともとそこに邪馬台国はなかったわけですから。)
ところで、卑弥呼の跡を継いだ女帝の“壱与”って、“いよ”と読むのでしょうかねぇ~。だとすると、愛媛県にとって、もっと面白い展開になりそうな予感がするのですが…。
……(その7)に続きます。
執筆者

株式会社ハレックス
前代表取締役社長
越智正昭
おちゃめ日記のタグ
おちゃめ日記のアーカイブス
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (8)
- 2018年4月 (11)
- 2018年3月 (9)
- 2018年2月 (9)
- 2018年1月 (9)
- 2017年12月 (15)
- 2017年11月 (13)
- 2017年10月 (13)
- 2017年9月 (13)
- 2017年8月 (16)
- 2017年7月 (17)
- 2017年6月 (14)
- 2017年5月 (14)
- 2017年4月 (12)
- 2017年3月 (16)
- 2017年2月 (12)
- 2017年1月 (11)
- 2016年12月 (12)
- 2016年11月 (16)
- 2016年10月 (12)
- 2016年9月 (12)
- 2016年8月 (20)
- 2016年7月 (13)
- 2016年6月 (14)
- 2016年5月 (11)
- 2016年4月 (20)
- 2016年3月 (15)
- 2016年2月 (14)
- 2016年1月 (12)
- 2015年12月 (12)
- 2015年11月 (15)
- 2015年10月 (17)
- 2015年9月 (20)
- 2015年8月 (15)
- 2015年7月 (14)
- 2015年6月 (15)
- 2015年5月 (9)
- 2015年4月 (16)
- 2015年3月 (18)
- 2015年2月 (15)
- 2015年1月 (20)
- 2014年12月 (14)
- 2014年11月 (16)
- 2014年10月 (21)
- 2014年9月 (24)
- 2014年8月 (24)
- 2014年7月 (21)
- 2014年6月 (14)
- 2014年5月 (3)